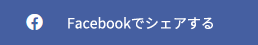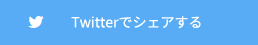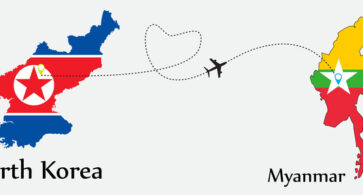世紀の大発明
多くの方々が意外と気づいていない履物に地下足袋(じかたび)があります。今でも外を歩くと時々見かけるものです。もともとは普通の足袋に近い形をしていて、足首の所をもう少し長く作り、さらに足袋の地に当たる部分につま先からかかとまで、生ゴムのような柔らかいゴムをびっしり貼り付けたものです。これにより、布の足袋だけでは得られなかったクッション性と耐久性が生まれました。これは世紀の大発明です。
地下足袋の良さは西洋の靴と比較するとさらに明確です。地下足袋の方は小さな石を踏んでも痛くなく、足が守られるうえに布地は水を含んでも乾きが早いので、多少ぬかるんだ場所でも動きやすいのです。一方、西洋の靴は水が入ってきて蒸れたり、乾きにくかったりします。靴のサイズが合わないと、靴ずれも起きます。地下足袋にはそういった不快さはありません。

石橋正二郎
伝統的な足袋にゴムを組み合わせるという発想でもって、実用性と快適さを同時に実現した男が石橋正二郎です。ブリヂストンの創業者です。「橋」(bridge)と「石」(stone)をあえて入れ替えて「ブリヂストン(Bridgestone)」と名づけたのは有名な話ですが、その始まりはタイヤ以前に地下足袋でした。地下足袋は土木作業や農作業の現場で消耗品として何百万足も売れ、1年目から大成功を収めたそうです。
土建屋さんたちは年に3~4足、履き潰すので、切れ目なく売れていくわけです。その結果として、石橋氏は巨万の富を築き、世界的なタイヤメーカーへと成長していきました。足の裏全体に柔軟なゴムを施すという、誰も考えつかなかった発想が日本の産業史を塗り替え、世界進出への扉を開いたのです。
高い実用性
現代でも地下足袋をこよなく愛し、仕事で用いている人々もたくさんおります。例えば、浅草で人力車をひく車夫や祭りの担ぎ手、建築現場のとび職などにも多く見られます。彼らは毎日、長距離を動き回ったり、重いものを担いだりしますが、地下足袋なら足の指がしっかり使えるので踏ん張りが効き、バランスも取りやすいのです。特に足の親指がほかの指より大きいのは、ここに力を集める特性が備わっているからだといわれます。
西洋の靴のように足全体を固定することはしないので、動きやすく、体の構造をしっかりとおさえた日本屈指の履物なのです。それは人間工学的な観点からも安全で機能的な履物と言えるのではないでしょうか。
明治政府が西欧式の軍隊を取り入れてもなお、日本の伝統的な履物である草履や足袋の改良を重ねていき、地下足袋のような独自の履物を開発していたらどうなっていたでしょうか。靴擦れや病気に悩まされることもなければ、靴の生産力という点でも苦戦しなかったと思います。戦況にも変化が生じていた可能性は否めないでしょう。日本軍の多くは戦う前に、まさに「足元」から崩れたのです。私はその悲劇を知っていますので、なおさら腹が立つのです。
西鋭夫のフーヴァーレポート
下駄と日本人(2021年10月下旬号)-5
この記事の著者
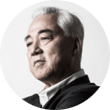
西 鋭夫
1941年大阪生まれ。関西学院大学文学部卒業後、ワシントン大学大学院に学ぶ。
同大学院で修士号と博士号取得(国際政治・教育学博士) J・ウォルター・トンプソン広告代理店に勤務後1977年よりスタンフォード大学フーヴァー研究所博士号取得研究員。それより現在まで、スタンフォード大学フーヴァー研究所教授。
西 鋭夫

1941年大阪生まれ。関西学院大学文学部卒業後、ワシントン大学大学院に学ぶ。
同大学院で修士号と博士号取得(国際政治・教育学博士) J・ウォルター・トンプソン広告代理店に勤務後1977年よりスタンフォード大学フーヴァー研究所博士号取得研究員。それより現在まで、スタンフォード大学フーヴァー研究所教授。