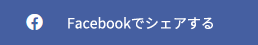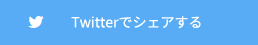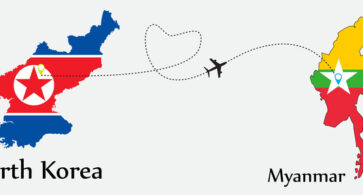From:岡﨑 匡史
研究室より
「銀シャリ」と呼ばれた白米は、かつて高級品でした。
日本では江戸時代まで石高制が取られていたように、お米により経済が周り、軍事力を測る物差しの基準としても用いられた。
コメは軍事物資。
それだけ、お米に価値があった。
私たちが普段食べている白米は、庶民にとって憧れの的だった。
日本陸軍
日本陸軍は、「白米」(銀シャリ)にこだわった。海軍に対抗して兵士を集めるために、陸軍に入れば「白米」にありつけると宣伝してからである。
東北地方の寒冷地では、白い米を腹一杯食べることは夢のまた夢であった。銀シャリが提供される陸軍に憧れて、東北の寒村地の若者たちは陸軍に志願した。
銀シャリの弊害が現れる。それは脚気になる兵士が多かったことだ。脚気は、ビタミンB1の欠乏によって起こる病気で、足の感覚が麻痺したり、すねがむくむ。
当時、「結核」と「脚気」は、二大国民病であり、脚気は「贅沢病」とも呼ばれていた。白米ばかり食べて、副食が少なかったので栄養バランスが悪かったからである。
漬物の効用
脚気を予防するために、漬物が重宝された。
漬物がエネルギー源になる訳ではない。
梅干しは防腐、伝染病予防に効果がある。沢庵を長く漬けるとビタミンCを失ってしまうが、ぬか漬けにすればビタミンBが含まれる。
漬物は、貯蔵性・栄養面・便通の改善・歯の衛生・食欲増進などさまざまな効果がある。
ー岡﨑 匡史
PS. 以下の文献を参考にしました。
・佐藤洋一郎『米の日本史』(中央公論新社、2020年)
・湯澤規子『胃袋の近代』(名古屋大学出版会、2018 年)
この記事の著者
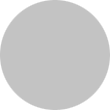
岡﨑 匡史
日本大学大学院総合科学研究科博士課程修了。博士(学術)学位取得。西鋭夫に師事し、博士論文を書き上げ、著書『日本占領と宗教改革』は、大平正芳記念賞特別賞・国際文化表現学会学会賞・日本法政学会賞奨励賞を受賞。
岡﨑 匡史

日本大学大学院総合科学研究科博士課程修了。博士(学術)学位取得。西鋭夫に師事し、博士論文を書き上げ、著書『日本占領と宗教改革』は、大平正芳記念賞特別賞・国際文化表現学会学会賞・日本法政学会賞奨励賞を受賞。