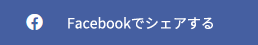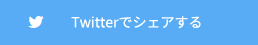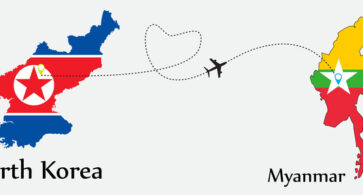地獄絵図
戦車が人々を轢き殺して進撃した後、戦車兵たちはいっせいに車外へ降りてきました。全員がペンチを持っていたようですが、何に使ったかわかりますか。彼らは、死んだ男や女、あるいは死にかけた人たちの口を無理やり開き、当時はよくあった金歯や銀歯をバチン、バチンと抜き取っていったのです。生きていようが、死んでいようが関係ありません。次々と歯を抜いていく。そして、指輪をしている人を見つけたら、特に女性に多かったそうですが、死体からは指輪がなかなか外れませんから、ペンチで指ごと切り落としたようです。

このおじさんは、それをすぐそばで見ていたのです。そして、まったく抵抗はできませんでした。その後、シベリアの奥地に連れて行かれ、収容所に入れられました。そこには500〜600人ほどが収容されていたそうです。仕事は、延々と広がる森林の伐採でした。しかし、食べ物はほとんど与えられませんでした。その結果、そこで収容されていた多くが栄養失調となり、免疫力が低下して、バタバタと倒れていったようです。
朝起きると、必ず誰かが死んでいる。それも1人や2人ではなく、10人、20人と次々に命を落としていきました。そして、だんだんと寒さが増してくると、埋葬しなければならないのですが、その地面が問題でした。気温はマイナス10度、20度、30度と下がり、地面はまるで岩のように凍りついていて、まったく掘ることができなかったのです。仕方なく、木造の冷たいバラックの外に遺体を積み上げるしかありませんでした。
極寒の地
生き残った者たちは、死体から靴を脱がせ、ボロの軍服も脱がせました。自分たちがそれを使いました。戦争が始まり、シベリアで捕まったときは夏でしたから、日本の兵隊たちは皆、夏服を着ていたのです。皆さん、日本の冬でもコートがなければ寒いですよね。シベリアの冬はそれどころではなく、マイナス20〜30度の世界です。
そんな中で遺体が積み重ねられていくと、冷凍庫から冷凍食品を取り出したときのようにガチャッとくっついていて離れません。遺体同士が凍りついて、剥がれなくなっているのです。
しかし季節がかわるともちろん溶けていきます。そうすると今度は「腐って臭いが出る前に埋めろ」とソ連兵たちは命じました。彼らはツルハシを持ってきて、その反対側には大きなジャガイモの袋を置いたそうです。そして、「このツルハシで死体を動かして埋めた者には、このジャガイモをやる」と言うのです。
引き剥がし作業
皆、極度の飢えに苦しんでいましたから、ジャガイモの袋を見ただけで「俺がやる」とボランティアが次々に手を挙げました。そしてツルハシを手に取りました。それを使って、遺体と遺体のあいだに差し込んで剥がそうとするのですが、暖かくなってきたとはいえ、そんな簡単にいくわけがありません。
ガチン、ガチンと音を立ててツルハシを押し込み、摩擦で氷を溶かしていくのです。すると、あるときおじさんが言っていました。「氷が溶けたら血が流れてきた」と。そりゃそうでしょう。凍りついていた血が溶け出してくるわけです。そしてそれを見た者たちは「まだ、生きているのではないか」と錯覚し、恐ろしくなってその場で吐いてしまいました。
それでもこのイクラおじさんは、「俺はこんなところで死にたくない」と言って、吐きながらも作業をやり抜いたそうです。そして、そのジャガイモで命をつなぎ、生き延びたと語っていました。シベリア抑留というのはそういう話です。「抑留」という言葉は、その現実を記述する上ではあまりにも美しすぎる言葉だと思います。
西鋭夫のフーヴァーレポート
シベリア抑留(2021年9月上旬号)-2
この記事の著者
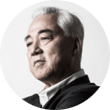
西 鋭夫
1941年大阪生まれ。関西学院大学文学部卒業後、ワシントン大学大学院に学ぶ。
同大学院で修士号と博士号取得(国際政治・教育学博士) J・ウォルター・トンプソン広告代理店に勤務後1977年よりスタンフォード大学フーヴァー研究所博士号取得研究員。それより現在まで、スタンフォード大学フーヴァー研究所教授。
西 鋭夫

1941年大阪生まれ。関西学院大学文学部卒業後、ワシントン大学大学院に学ぶ。
同大学院で修士号と博士号取得(国際政治・教育学博士) J・ウォルター・トンプソン広告代理店に勤務後1977年よりスタンフォード大学フーヴァー研究所博士号取得研究員。それより現在まで、スタンフォード大学フーヴァー研究所教授。