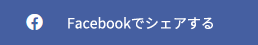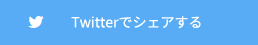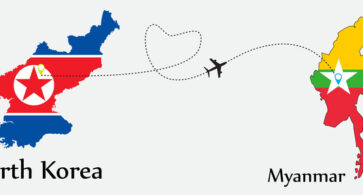シベリア抑留
終戦間近の1945(昭和20)年8月8日、ソ連は日本に対して宣戦布告を行い、翌9日には満洲国への進撃を開始しました。その後、ソ連軍は樺太や千島列島を次々と占領していきます。この結果、およそ60万人の日本軍将兵および一般市民がソ連軍に捕らえられることとなりました。日本とソ連の国交が回復されるまで、短い人で数年、長い人では10年以上も、ソ連各地の収容所で強制労働に従事させられたのです。これがいわゆる「シベリア抑留」です。

現在では「シベリア抑留」という言葉を耳にすることはほとんどなくなりましたが、私は米国留学中にとても貴重な体験をしました。23~24歳の夏のことです。アラスカ半島からアリューシャン列島にかけての小さな島々のひとつに、デルモンテの鮭缶詰工場がありました。それまで鮭の卵を海にボンボン捨てていたのを、日本のある会社が目をつけたのです。「その卵を買いたい。イクラを作るのに使いたい」という話でした。
アメリカ人たちからすれば、今まで捨てていたものを買ってくれるのだから大歓迎です。そうして北海道からイクラ職人がやって来ました。けれども、このおじさんは英語が話せません。そこで、通訳を探すことになり、シアトルにあるワシントン大学に「日本人でアリューシャン列島に行ける者はいないか」という話が舞い込みました。私はちょうど金欠で困っていたこともあり、手を挙げました。場所を尋ねたところ、「缶詰工場だ」と聞かされました。そこで日本からやってきたイクラ職人と会いました。
抑留経験
このおじさん、私の顔をちらりと見て、すぐに横を向くような人でした。嫌われたのではありません。むしろ「戦争を経験していない若い男の顔を見たくない」とでも言うような、そんな印象でした。これは冗談ではないですよ。
1ヶ月ほどたってようやく口をきいてくれるようになり、「戦争中はどちらにおられたのですか?」と聞くと、「満洲だ」と答えました。私は当時、満洲の事情をよく知らなかったので、「よく生き延びられましたね」と言うと、「うん」との返事。「ソ連軍に捕まったのですか?」「そうだ」とやりとりが続くと、そこからぽろぽろと話し始めました。一度口を開いたら、もう止まらない。そういう感じでした。
このおじさんは兵隊として満洲でソ連軍に捕まったのですが、そのとき100人、1000人、さらには万の単位で日本人が次々と捕らえられていったそうです。そしてズルズルと奥へ奥へと連れて行かれたようでした。彼はソ連軍の戦車が入ってくるのをこの目で見ていたそうです。皆さん、戦車がどう動くかご存知ですか。
今でもひょっとしたらアフガニスタンなどで似たようなことが起きているかもしれませんが、ソ連の戦車は日本軍のものよりもずっと大きく、約2倍ほどのサイズがあったといいます。その巨大な戦車が何百台も満洲の広大な平野を縦横無尽に突進してきました。日本の兵隊たちや一般市民、子どもたちは必死で逃げました。しかし、その上を戦車がゴーッと轢いていくのです。いわば「殺しながら」進撃していく、そんなことが起きておりました。このイクラ職人はそれを間近で見たのです。
西鋭夫のフーヴァーレポート
シベリア抑留(2021年9月上旬号)-1
この記事の著者
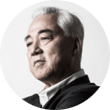
西 鋭夫
1941年大阪生まれ。関西学院大学文学部卒業後、ワシントン大学大学院に学ぶ。
同大学院で修士号と博士号取得(国際政治・教育学博士) J・ウォルター・トンプソン広告代理店に勤務後1977年よりスタンフォード大学フーヴァー研究所博士号取得研究員。それより現在まで、スタンフォード大学フーヴァー研究所教授。
西 鋭夫

1941年大阪生まれ。関西学院大学文学部卒業後、ワシントン大学大学院に学ぶ。
同大学院で修士号と博士号取得(国際政治・教育学博士) J・ウォルター・トンプソン広告代理店に勤務後1977年よりスタンフォード大学フーヴァー研究所博士号取得研究員。それより現在まで、スタンフォード大学フーヴァー研究所教授。