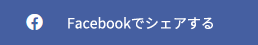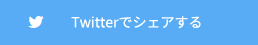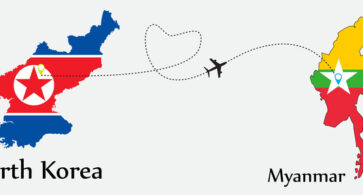From:岡﨑 匡史
研究室より
学習院大学で日本中世史を専攻された天皇陛下(第126代)は、水の研究者としても知られている。
1983(昭和58)年6月から2年4ヶ月、オックスフォードの大学院にご留学。
滞在中、陛下は「ヒロ」と呼ばれていた。外国人にとって「Naruhito」は発音しにくかったからだ。
また、陛下の「傘」が盗まれた体験もしている。図書館に置いておいた傘が誰かに持ち去られてしまい、ずぶ濡れになって寮に戻らざるを得なかった。
テムズ川
オックスフォードでは、英国の水上交通史の研究に着手する。なぜなら、学習院では室町時代の海上交通の研究をしていたからだ。川は、海上交通を担う経済の大動脈。
テムズ川はオックスフォードに沿うように流れている。陛下はテムズ川に親しみを感じており、テムズ川に関する史料も入手しやすいと考えた。
しかし、17世紀頃までのテムズ川に関する史料はラテン語で書かれていた。ラテン語を習得するとなると、二年間という修士課程ではとうてい克服できない。さあ、困った。
アーカイブズ調査
研究対象の時代を英語の文献が豊富な18世紀に絞りこんだ。そして、テムズを行き来した二大物資である石炭とモルトなどの農産物に焦点をあてた。
さらに、指導教官のアドバイスで、オックスフォードのアーカイブズ、英国の国立公文書館で研究調査を実施する。
徳仁親王は、アーカイブズ調査の思い出を次のように書き留めている。
「はじめのうちは史料の読み方や解釈に時間を要したが、こういった場所で生の史料に当たり、ある時は読みにくい文字に奮闘しながら、またある時は舞い上がるホコリを吸いながら取り組むことは、何か史料を通してその時代の温もりを感じるような気がしてひじょうに嬉しいことであった。また、文書館の人々はたいへん親切で、どうすればその史料を見いだせるか、探し方を十分に熟知していると見受けられた。」(徳仁親王『テムズとともに』)
こうした苦労を重ねながら修士論文『The Thames as Highway』(交通路としてのテムズ川)が完成していく。
ー岡﨑 匡史
PS. 以下の文献を参考にしました。
・徳仁親王『テムズとともに』(紀伊國屋書店、2023年)
この記事の著者
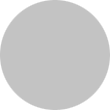
岡﨑 匡史
日本大学大学院総合科学研究科博士課程修了。博士(学術)学位取得。西鋭夫に師事し、博士論文を書き上げ、著書『日本占領と宗教改革』は、大平正芳記念賞特別賞・国際文化表現学会学会賞・日本法政学会賞奨励賞を受賞。
岡﨑 匡史

日本大学大学院総合科学研究科博士課程修了。博士(学術)学位取得。西鋭夫に師事し、博士論文を書き上げ、著書『日本占領と宗教改革』は、大平正芳記念賞特別賞・国際文化表現学会学会賞・日本法政学会賞奨励賞を受賞。